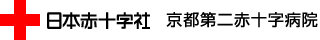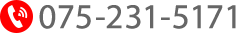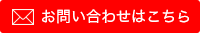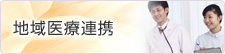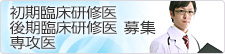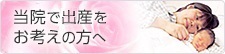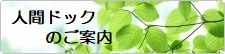診療方針
手術室と聞くと、ドラマにあるような個性的で職人的な外科医や麻酔科医が常人離れした技術を披露するような場所を想像されるかもしれません。しかしながら現実は違います。現在の手術室はチームなくしては全く機能しません。麻酔科医は手術が速やかにかつ安全に進行するよう術者をサポートしますが、看護師や臨床工学士等のメディカルスタッフの助けなしでは成り立ちません。私達の手術中の主な役割はストレスから患者さん守ること、そして術後のスムーズな回復につなげられるよう、質の高い麻酔管理と効果的な鎮痛法を施行することです。
昨今、手術後の回復に重点をおいて介入を行う回復プログラムが重要視されています。術前の禁煙、絶食期間の短縮、術前後経口補水法、早期リハビリテーション、術後早期経口栄養管理などが含まれます。麻酔科医はこの中で重要な役割を果たしますが、上記のごとく一人ではできません。チームで手術およびその前後=周術期に対応してゆく時代となっています。私達麻酔科医はこの周術期医療の質の向上に努めていきます。
症例数・治療実績
| 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
| 総手術件数 | 6,188 | 6,383 | 6,347 | 6,474 |
| 麻酔科管理件数 | 3,918 | 4,285 | 4,210 | 4,335 |
手術部位別件数
| 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
| 総数 | 3,918 | 4,285 | 4,210 | 4,335 |
| 小児 | 60 | 47 | 49 | 30 |
| 帝王切開 | 65 | 70 | 45 | 43 |
| 心臓血管外科 | 113 | 95 | 108 | 138 |
| 胸部外科 | 206 | 211 | 178 | 188 |
| 脳外科 | 109 | 115 | 100 | 79 |
連携病院・開業医の先生方へ
最近では複数の合併症を有する患者さんや御高齢の患者さんの手術適応も拡大され、当科においても充分な合併症対策を講じるとともに、患者さんやご家族とも充分に話し合いをさせていただき、麻酔管理について患者さんとご家族、主治医(外科医)、麻酔科医がそれぞれの立場からおたがいに納得の出来る周術期管理を行なえるよう努力しています。貴院から御紹介いただきました患者さんにつきましても万全の備えをもって対応しています。貴院より当院へ患者さんを御紹介の際には,ご処方の薬剤やアレルギーの既往等、より多くの情報のご提供を、また緊急手術に際しましてはより正確な診療情報を得るためのご協力をお願いいたします。当院は京都府立医科大学麻酔科専門医研修プログラムの基幹研修施設に位置付けられています。加えて、福井大学と麻酔科専門医研修交流プログラムを策定しました。
スタッフ
| 職 名 | 名 前 | 卒業年度 | 専 門 | 資 格 |
|
副院長 |
|
H4 | 麻酔全般 | 日本麻酔科学会麻酔科指導医 日本麻酔科学会・日本専門医機構 麻酔科専門医 日本集中治療医学会専門医 日本救急医学会救急科専門医 日本急性血液浄化学会認定指導者 |
| 第2麻酔科 部 長 |
 望月 則孝 望月 則孝 |
H7 | 麻酔全般 | 日本麻酔科学会麻酔科指導医 日本麻酔科学会・日本専門医機構 麻酔科専門医・認定医 |
| 副部長 |  三田 建一郎 三田 建一郎 |
H18 | 麻酔全般 | 日本麻酔科学会・日本専門医機構 麻酔科専門医・認定医・指導医 |
| 医 師 | 有吉 多恵 | H17 | 麻酔全般 | 日本麻酔科学会・日本専門医機構 麻酔科専門医・認定医・指導医 |
| 医 師 | 坂井 麻祐子 | H20 | 麻酔全般 | 日本麻酔科学会麻酔科指導医 日本麻酔科学会・日本専門医機構 麻酔科専門医 日本麻酔科学会 麻酔科認定医 日本心臓血管麻酔学会 日本周術期経食道心エコー認定試験合格証 |
| 医 師 | 岡林 志帆子 | H21 | 麻酔全般 | 日本麻酔科学会・日本専門医機構 麻酔科専門医・認定医・指導医 |
| 医 師 | 長谷川 知早 | H23 | 麻酔全般 | 日本麻酔科学会・日本専門医機構 麻酔科専門医・指導医 日本区域麻酔学会認定医 |
| 医 師 | 佐々木 敦 | H24 | 麻酔全般 | 日本麻酔科学会・日本専門医機構 麻酔科専門医・認定医 日本区域麻酔学会認定医 |
| 医 師 | 植田 有里恵 | H30 | 麻酔全般 | |
| 医 師 | 田中 遥 | H30 | 麻酔全般 | 日本麻酔科学会・日本専門医機構 麻酔科専門医 |
| 医 師 | 溝部 周 | H31 | 麻酔全般 | |
| 医 師 | 良宇都 有那 | R5 | 麻酔全般 |